昨日のエントリーで紹介した書籍、『卓球 知識の泉 百二十年の歩みをエピソードでつづる世界卓球文化史』。
卓球が誕生してから120年の歩みを、豊富なエピソードでつづっている本なのだが、たくさんの卓球の知識が詰まりに詰まっているので、本書から卓球雑学をもう少し紹介したいと思う。
本日紹介するのは、超長時間の試合について。
1936年(昭和11)年に開催された、第十回世界選手権プラハ大会でそれは起こった。
第一回大会以来、順調に発展してきた卓球競技がこの超長時間の「見ていておもしろくない試合」によって、危機を迎えた。
プラハ大会で続出した超長時間試合、その代表的なエピソードを二つご紹介する。
一つ目は、男子団体のポーランドとルーマニアの試合でのこと。
トップに出場したのは、ルーマニアのエースのパネスと、この大会を含む3大会で世界2位となっているポーランドのエーリッヒ。
パネスは〝石で作った壁〟のような堅実な守備型で、エーリッヒは守備も攻撃もうまいオールラウンド・プレーヤー。
戦略家のエーリッヒが考えた戦術は、ツッツキで徹底的に粘り、それによってパネスを疲れさせること、そして相手チームのやる気までなくさせるというもの。
試合が始まった。その最初のポイントで、二時間を越えるツッツキの粘りあいが起こった。当時は時間制限ルールもないし、審判員は開始時刻を計測する必要がなく、計測していない。このため、正確な所要時間は分からない。二時間五分説、二時間十二分説などがある。あまりにもラリーが続き、首を左右に何百何千回と回すうちに審判員が首をいため途中で交代したとか。国際卓球連盟(ITTF)は、打開策を協議するため裁定委員会を開こうとしたところ、メンバーの一人が、今プレーしているとあってコートサイドで会議を行ったとか。パネスが、君は攻撃もできるのになぜ攻撃しないのか、とエーリッヒを挑発したとか。いろんな話が伝わっているが、エーリッヒは挑発にも乗らず、事前に考えた戦術どおりに徹底的に粘りぬいて勝利をおさめた。
そしてもう一つの超長時間試合は、男子団体決勝のオーストリア対ルーマニア戦で起こった。
初日の夜9時30分に始まった試合は、午前3時30分までかかって、やっと2対2だった。
同じ週の別の日に続きが行われ、オーストリアが5対4で初優勝した。
2日がかり、あわせて11時間もかかった試合だった。
ネットが今よりも約1・9センチ高い上に、今のような〝すごい威力の攻撃球が出るラバー〟がなく、「守備有利の時代」であったこと、当時のヨーロッパではカットを得意とする守備型が多かったことなどから、ツッツキ(カット対カット)の粘り合いが珍しいことではなかった。だが、なぜ三十六年大会で、超長時間ラリーが続出したのか。それは、開催国のチェコスロバキアが「指で押したら台がへこむのではないか」と思われるほど、軟らかいテーブルを使ったからであった。台が軟らかくて、ボールのはずみが低いほど、攻撃より守備が有利となる。男子シングルスで地元代表の守備型選手コラーが優勝したが、チェコスロバキアにとって良いテーブルであり良い大会であった、ということをレイドが『ビクター・バルナ』の中で書いている。このような超長時間試合の続出は、卓球競技の発展にとって、まさに〝危機〟と呼ぶべきものであった。
指で押したらへこむのではないかと思われるほど軟らかい卓球台って、いったいどんな台なんだ!
開催国なら何をしても許される時代だったのであろうか・・・。なぜそんな台が認められたのか、実に不思議である。
ちなみに、国内全国大会の最長時間試合は、今考(青森商)対宮川顕次郎(青森中)の激闘であるという。
それは昭和八年(古っ!)の第二回全国学校対抗での出来事。
(前略)ライバルの両校が決勝で対戦し、両校のエースは共にカットとショートを得意とする粘り強い選手。国内は木のラケットによる軟式卓球の時代で、今日のようにカット対カットつまりツッツキによる粘り合いではなくショートで粘り合った。時には1ポイントのラリーが三千回も続く。のちに今考の義父となる山本弥一郎が、途中で夕食に出かけ、もどってみたら、得点が同じままだったという。夜六時に始まり、会場の門限の十時になっても決着がつかない。高村義雄審判長が、続きは青森に帰ってからやるように、と言ったが、対抗意識の強い両校は、応援団も興奮しており、承知しない。やむなく銀座裏の卓球研究所に移動して十時半に再開。終わったのが、なんと夜中の一時半だったという。(後略)
「木のラケットによる軟式卓球」というのが時代を感じさせるなあ。
スマッシュでがんがん攻めていくとミスして自滅するから、慎重につないでいく戦術になるということでしょうね。
えー、そんなわけで、本日の雑学紹介は以上です。
今後もいろんな卓球雑学を収集し、紹介していく所存です。
では、また!










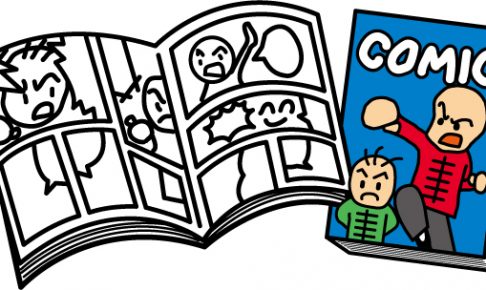



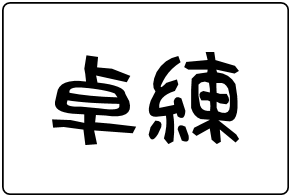


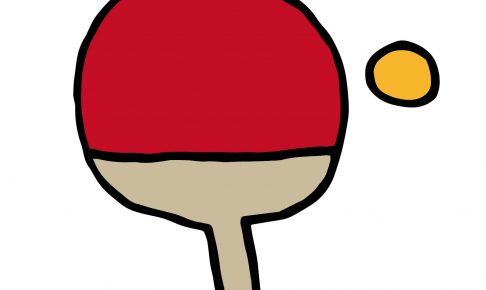




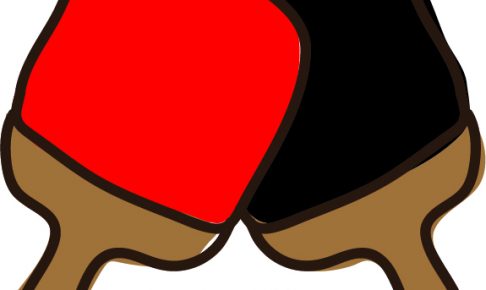

コメントを残す